|
映画「つぐみTUGUMI」のサイト |
||
|
<松竹映画「つぐみTUGUM」を語るサイトです。> |
||
| ■松竹映画「つぐみTUGUM」 | ||
| ■松竹映画 「つぐみTUGUM |
|
|
| 《「つぐみTUGUMI」詳細場面集》 | ||
| 映画の場面を時間で追ってみました。■の前の数字はカウンター。最初の映像が出たところを0'00スタートで計測。数秒の誤差はあります。<>の中は引用者の感想。 |
エンドロールの中身 牧瀬里穂 中嶋朋子 白鳥靖代 安田伸 渡辺美佐子 あがた森魚 財津和夫 吹越満 高橋節子 ■■まどか ■■麻子 高橋源一郎 歌■寅右衛門 なんきん 水野栄治 砂川真吾 野々村仁 辻木良紀 |
|
| ↑このページのトップへ | ||
| いろいろな話題 | ||
| ■映画の魅力 |
|
|
| ■好きな場面■ |
|
|
| ■就航船こばるとあろー |
|
|
| ■梶寅旅館のこと |
|
|
| ■つぐみと子ども |  ■「つぐみを好きな子どものこと」 ■つぐみの性格を側面から表現していて、原作にはない子どもとつぐみとの一連の交流がいい。 子どもが対等に相手をする大人はいつの時代も素敵である。 ○冒頭、子どもに尻をラケットでぶたれて、そのあとで子どもの尻を蹴飛ばすのは、<蹴るだろうと思ったら案の定>予想どおりのシーンだった。 蹴飛ばされた子ども、彼はつぐみの友達である。蹴りを入れられても、つぐみに相変わらず着いて来る。つねに構ってもらいたいのだ。 ○つぐみが病院へ行く日と時間を知っていて、病院へ行く時は、必ずつぐみを待っている。 恭一が兄を訪ねて来た時、それはつぐみがちょうど病院へ出かける時間で、子どもは梶寅旅館の前で蠅叩きを手にして待っていた。 その後、つぐみと戯れながら病院に向っている。 ○海岸でつぐみ、まりあ、まりあの父がビーチパラソルの下にいるとき、彼も堤防の下にいて、トマトを食っている。蠅叩きは忘れていない。 ○つぐみはいないけれど、まりあが帰京する港へも来ていた。 ○ただ、まりあが松崎に帰郷した時もつぐみのそばにいた彼は、その時も、つぐみの尻を殴る。この時のつぐみの対応はもう少し脚本を煉った方がよかったような気がする。彼をうるさそうに、つまり普通に対応する ○もうひとつ、遊び的な要素を考えれば、もう2ヶ所くらいに子どもを登場させるのも効果的で面白かったはず。 これがあまり多いと主題が曇るので、映像のどこかに、安野光雅の「旅の絵本」のようにさりげなく。 |
|
| ■死を意識するということ |  ■58'00で喫茶店で藤内と会っているつぐみ「鼻から血が出てるぜ」の場面は象徴的。藤内にとって、つぐみは別の側にいる人間なのだ。 吹越満(映画「ホワイトアウト」での悪役的人物が良かった)演じる藤内が、「こんな気持ちひさしぶりなんだよ」と言って、「鼻から血が出てるぜ」と、つぐみからからかわれる。 不良グループのリーダーともあろうものが、つぐみごとき小娘に手玉にとられるのは、 つぐみの特別な存在にその理由がある。 つぐみの強さは隣り合わせの死を持っていることにある。いつでも自分の死を本気で俎上にすることができる人間。これは、普通の人間からすればすこぶる魅力に思えるのである。 自然死でない死を身の内に持っている人間だけにある不敵な強さ。 それは、普通の人には分かっていても、本当の理解はできない。 これは知識ではなく、感覚の問題なのである。 両親も周りの人間も誰もが、あそらくそれを知っているが、単なる知識であることと、その感覚を所有していることとは決定的に違うことなのだ。 中途半端なワルの不良も、もちろん理解できないこの強さを持ったつぐみには敵わない。 それは不良の最も憧れる「強さ」でもあるわけだが、だからこそ藤内はそういうつぐみに惹かれている。 藤内もその強さが欲しい。しかしそれは無理だ。車で正面衝突ゲームをしても、最後にハンドルを切ることになったり、百戦錬磨の剣豪でさえ、死生眼を持っている子どもの大五郎にはなれないのと同様。 |
|
| ■つぐみの配役について |
適役といえば、最初、つぐみの役を中嶋朋子が願ったそうだが、主演のつぐみは、牧瀬里穂が断然適役と思える。「東京上空へいらっしゃい」も良かったらしいが、「男はつらいよ」第47作「拝啓車寅次郎様」で、滋賀県長浜に住む、満男の先輩の妹・菜穂役も好演だった。牧瀬里穂は、こんな風な男っぽい役がよく似合う。
|
|
| ■原作と映画 |
■原作と映画のどちらがいいかということも議論されたことがあります。
「牧瀬里穂一世一代の当たり役」という人の一方で、「牧瀬のヒステリックな演技だけが印象的。駄作」「原作は大好きなんだけど映画版はいまいちだった」「原作と違うのは別にいいけど、映画としての価値ゼロだとおもう」「恭平が背広着てるのはなんだよ。社会人で仕事してるのはなんだよ。…小説の雰囲気台無し」という意見もありますが、小生は圧倒的に、小説より映画がいいと思うし、牧瀬里穂も適役だと考えています。
映画を先に見て、原作を読むと、各場面で頭の中に出演者が登場してくるので、これはどうしょうもありません。
原作を先に読んで、あるイメージを描いて、映画を見ると、「こりゃぁ違う」と思う人もいるでしょう。小生は、映画→原作でしたので全体的に違和感もなく、ネクタイをしている恭一、の方がしっくり来ました。
■原作と映画で、相違するところを探ってみました。 確認できないところがあるので、誰か教えて下さい。 1 まりあの母親は、つぐみの母親の政子さんの妹でしょうか?姉でしょうか? 原作では、「母の妹である政子おばさん」とある(中公文庫・P12)。 2 年齢のことですが、まりあとつぐみは同い年ではないのだろうか? 原作では、「陽子ちゃんが私より、私がつぐみより、ひとつ上だ」(中公文庫・P12)。 3 陽子ちゃんは、眼鏡をかけているのでしょうか? 原作では、「丸いメガネをかけたやさしい横顔で陽子ちゃんは笑った」とある(中公文庫・P38)。 4 ついでに疑問。まりあの父が東京へ戻る時に乗ったバスはどこ行き? 原作では、「まっすぐ東京へ向かう急行バス」とある(中公文庫・P134)。 |
|
| img src="tugumipho/123.jpg" width="200" height="140"alt="tugumi">■わがふるさと |
■ 旅館の前が海というロケーションはいいですね。 吉本ばなな氏が毎年、避暑に、なぜ松崎に行っていたのかはわかりません。 小生の母親の実家が、海水浴場を前にした大きな海の家、というような、泊まることはできないが、たくさんの部屋のあるいわば旅館のようなところでした。だから孫である自分にとっては快適な海辺の宿でした。毎年、一夏、その祖母の家で、海水浴をして、海を眺めて過ごしました。それで、旅館「梶虎」のイメージはたいへん身近なものです。 写真の正面は現在営業中の旅館ですが、右手の山付きに家がありました。 |
|
| ■「科作り君」について |
|
|
| ■劇中のテレビドラマ「少年オルフェ」について |
| |
| ■好きな場面 |
■これまで出された、映画「つぐみ-tugumi」の好きな場面は、
|
|
| 松崎紀行 | ■中江病院 |
■初めて松崎に行きました。といっても、伊豆半島は3度目。松崎は以前、通過しただけで、「関心がないとただ通過する町でしかない」というのが、典型的にわかります。
まず、中江病院です。 意外なところにありました。 写真を撮りました。待合室は年配者でいっぱいでした。受診者のふりをして中に入ればよかったかな。 <pho1は病院建物、pho2は藤棚、pho3は待合室> 

 |
■梶寅旅館へ |
■それから、中江病院の前の通りを進んで、看板がかなり薄くなっているまつもと青果の三叉路を右折すると、豊崎ホテル。
ここは松崎温泉のひとつ。やはり伊豆は温泉なのでしょうか?温泉半島である伊豆は、東伊豆に熱海、網代、伊東、宇佐美、北川、熱川、稲取、今井浜、中伊豆には伊豆長岡、大仁、修善寺、湯ヶ島、河津温泉郷、南伊豆には下田、蓮台寺、河内、下賀茂、そしてこの西伊豆には、土肥、堂ヶ島、松崎、岩地、石部、雲見などがあります。
ブログで見ると、どうも豊崎ホテルの4階の露天風呂から、梶寅旅館が俯瞰できそうな感じ。B&Bで、6955円(1人だと8530円)らしい。夕食は道路向いにあるレストラン民芸茶房で1050-3150円程度。Check-in15(最終23時まで)- Check-out10。
豊崎ホテルのすぐ先に、いよいよ、梶寅旅館です。単なる「宿の一軒」ではありません。他の宿と比べると何と魅力的な建物でしょう。
文化財審議委員が地元の文化財を見るときの気持ちってこんなのでしょうか?
初めてなのに、梶寅旅館の周辺は、何だか見慣れた風景です。
建物入口にある細長い看板には「つぐみの宿」とあります。ふむふむ、知っていたけど。
建物に向って入口の左上を見上げると、そこがつぐみの部屋。
何だか、青春時代に、付き合っている彼女か、あるいはただ憧れているという関係だけの女性の部屋を見上げているようで、今でいえば、まるでストーカー。
つぐみは恋愛の対象というよりむしろ、ひとつの存在なのだね。けれど「つぐみ」とは違う、もうひとつの恋愛的物語が思い浮かびそう。
つぐみのこの部屋は映画のカットで見ると、窓枠などが正にそのまま。「映画パンフに、つぐみの部屋は窓の外の景色をより良いものとするため、付近の山の中に仮設の建物を造り、その部屋を撮影では使用した、みたいな記述があったよう」といわれているので、撮影用に同じ構造の部屋をどこかに造ったというのは本当でしょうかね。
<pho1は旅館建物、pho2は玄関、pho3はつぐみの部屋> 


| ■梶寅旅館 | ■梶寅旅館の玄関は閉まっている。もちろん、営業はされていない。
人気のない旅館の玄関を、不審人物さながら覗き込むと、正面に、映画の時と同じ「善気迎人」の文字の額。
「善気迎人」とは、「思いやりのある気持ち・態度で人を惹きつける」とか「善意が人を招き入れる」「善良な人を迎え入れる」とかいわれているが、
旅館人の姿勢として「気持ちよく人を迎える」ということだろうな。
それにしても、当時、覗き込んだ旅館の玄関は想像していた以上にかなり狭かった。
まぁ、映画ってそんなものだけれど。
そうすると、旅館の浴槽も、物干し台、まりあの離れの部屋も狭いのかな。 玄関に置いてあった青い花瓶も映画の時のまま。
不思議に建物の中を見たいなどとは思わない。もちろん人がいれば、迷うことなく、積極的に見学させてもらうはずだけれど。
映画の中では、
50'05■そうしている内に、青年の兄が階段の上から覗き下ろし「よぉ」
青年「やぁ」
青年の兄「上がれば」
青年、上がるのを見送る父親。つぐみは靴を履き、出て行く。
という場面で、画面の左上にその額が見えています。
<pho1は玄関内、pho2は額、pho3は映画の中の一場面。左上に同じ額の一部が見える> 


|
| ■民宿旅館梶寅 |
■「できれば旅館を再開したい気分だ」というのは、 「無理をしてでも再開してもらいたい」というのではもちろんなく、 了承されれば、旅館を、私自身が再開したいという意味です。 本格的な旅館経営でなくてもいいので、 民宿・梶虎旅館という名称のイメージ。 つまり、廉価で気楽に泊まれる宿。 自分で布団を敷くような宿。 1泊でなくて、連泊することも、余裕でできるような宿…。 新鮮な魚介類も食べられるが、自炊をするようなイメージの宿…。 ある部屋をミニシアターにしていて、毎晩「つぐみ-tugumi」を上映しているような宿…。 「セカチュウ」の人たちにも利用してもらえるような宿…。 そんな宿が理想的かな? そこで、思いついたのですが、「つぐみ2-tugumi-2」という映画、というか小説というか、そんなのができませんかねぇ? 時代は2010年代、夢が広がりますが。安田伸氏は亡くなりましたが、渡辺美佐子さんは存命だし。 もっとも、これは原作者次第のことですが。 |
|
| ■旅館と離れの間の通り |
■梶寅旅館の隣には瀬崎稲荷がある。その横合いの通りには、梶寅旅館の別館。 本館とは渡り廊下で結ばれている。この構造はちょっと珍しいと思う。 きっと、旅館の長い歴史があるはず。 この廊下は、映画の中で出窓のように植物の鉢が置かれていたところだろうと思う。 渡り廊下の下部には、あの裏玄関がある。「あの」というのは、まりあのケーキ屋での最後のバイトの夜、戻って来た場面のこと。まりあの母も旅館で働いていた頃、ここから出勤していた。 離れの格子窓を見た。「ぶす」の文字の外に見えたのもここだろう。 まりあ母子の住んでいたあの離れや、旅館の建物背後にあるであろう物干し台は見ることはできなかった。 <pho1は本館と離れとの間にある小路、pho2は離れの格子窓> 

| |
| ■瀬崎稲荷 |
■梶寅旅館の建物や、旅館に隣接する瀬崎稲荷神社、岸壁に舟の繋留された那賀川河口の風景は初めてなのに、何度も来たような気がする。何よりも那賀川のゆっくりとした流れがいい。
国道136号線が松崎の町に下って来る対岸の風景も懐かしい感じ。 ここは、かつて走ったことがある道だけど、通り過ぎただけの町。
|
|
| ■旧松崎港 | ■梶寅旅館から海の方に向う。
旅館からはわずかの距離。まりあを迎えに行くのも普通の感じ。 かつて就航船が接岸した岸壁は、往事の姿はほとんどない。 待合所も完全に寂れたままで放置されている感じ。 そこにいたのんびり人とは目を合わせただけで、その先、漁船の係留された先、松崎海岸が見える防波堤で釣りをしていた埼玉の御仁と話。奥さんは松崎の人という。 ここからは、松崎の海水浴場、松崎伊東園ホテルと伊豆まつざき荘の2つのホテルなどが見える。 映画撮影の時は、単なる防波堤だったのが、綺麗な階段になったりして雰囲気が違っている。
<pho1は松崎海岸、pho2は象徴的な赤い標識と沈む夕陽の作画したもの> 
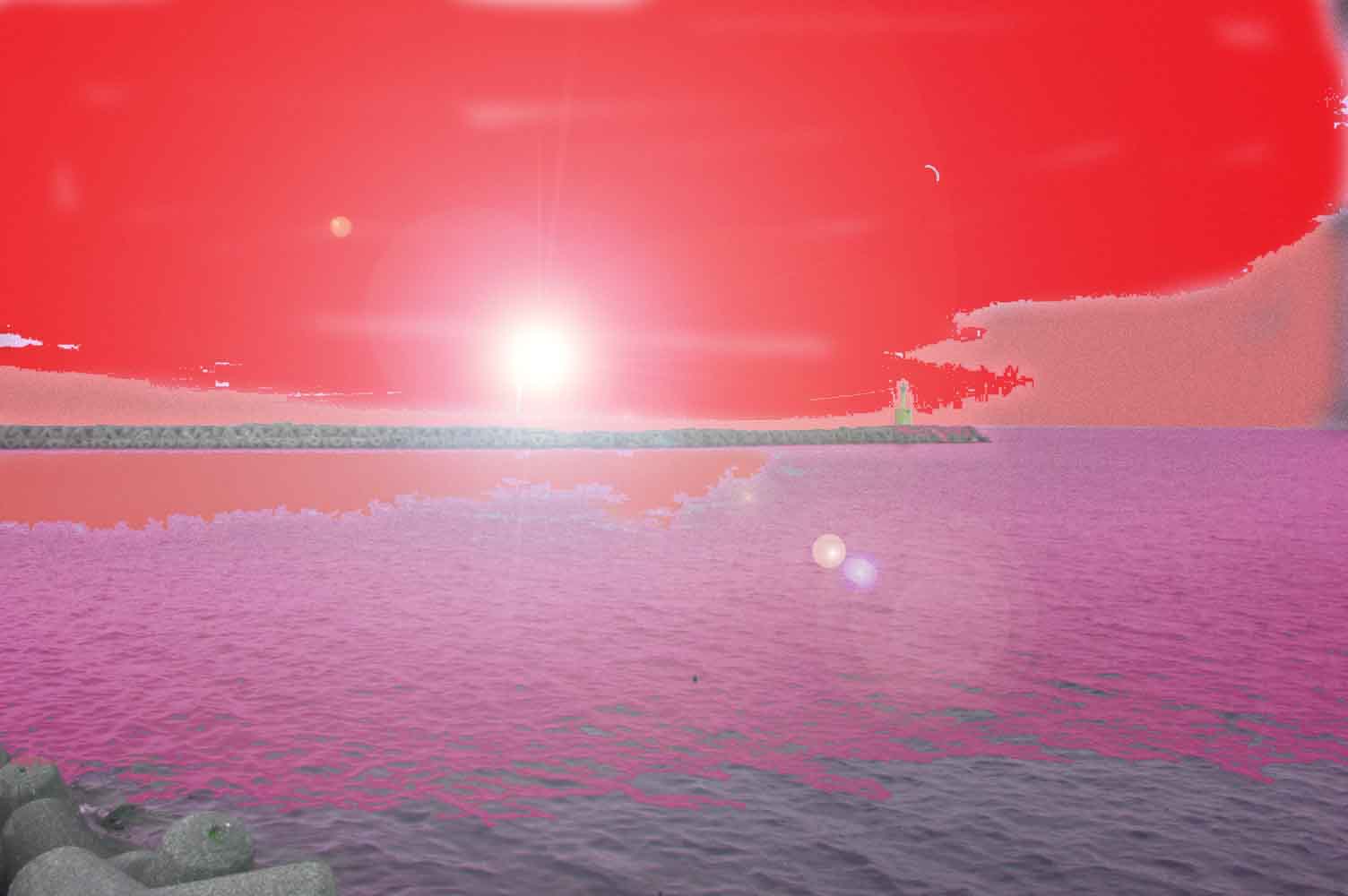 |
|
| ■松並木の通り |
■船乗り場から豊崎ホテルと民芸茶房の近くにある漁協直売所に行く。ここは映画の最初の方で、つぐみが中江病院に出かけた際、陽子と行き会って、歩いて行った最初のポイント。
漁協直売所の横にあった、老人の坐っていたあの消防ポンプ小屋は老朽化のため2009年に取り壊され、いまは駐車スペースになっている。
直売所の中には、平日あるいはオフシーズンという状況で、あまり商売熱心にはなれない担当者が1人いた。
北側には松並木が続く。
はやまという薩摩揚げの店があった。
海水浴場に立ち寄ってから、ときわ大橋を経て、松崎町観光協会へ。
<pho1は消防小屋跡地つまり松並木の北方向、pho2は松並木の南方向を見る>


| |
| ■松崎人と |
■ときわ大橋の上で、散歩をしていた地元の80代の老人と話。若い頃は松崎の山で焼かれた木炭を沼津の方まで船で運んでいたという。
毎年行なわれている夏祭りの夜店の数が減ったこと、那賀川の灯籠流しの数も少なくなったことなどを聞く。もしかして梶寅のかつての時代を知っていたかどうか、残念ながら聞き漏らしてしまった。
ところで、映画ではつぐみは中江病院へ行くのに、ときわ大橋を経てから病院というルートだった。
中江病院は、まつもと青果からまつざき荘へ行く通りにあるのだから、完全に遠回りになるはず。あるいは町内の散歩を兼ねていたつぐみの行動かなとも思えるけれど、どうなんだろう。
<pho1はあの「けとばし」の場所>

|
|
| ■松崎町観光協会 |
■ときわ大橋の先にある観光協会の建物はやはりなまこ壁。 ここで初めて地元の地図を入手。 「伊豆松崎温泉郷ごあんない図」の他、時代の流れであろうか「人気ドラマ世界の中心で愛をさけぶの松崎町ロケ地マップ」があった。それなりに詳しい(のだろう、見てないからわからんけど)。 映画の公開のときから時間はずいぶん経ったけど、「つぐみのロケ地マップ」も誰か作れよ! 松崎町観光協会のリーフレットは、この他に、 「伊豆松崎スケッチコンクール」「伊豆松崎心に残る写真コンクール」もあった。 うむ、それなりのことがやられているな。 観光協会から、なまこ壁通りをちょっと見て、浜丁橋の方へ戻る。<pho1は松崎町観光協会の建物、pho2はなまこ壁通り>

 | |
| ■那賀川沿い |
■那賀川に架かる浜丁橋の畔にあるなまこ壁の依田邸に行く。すぐそばには船泊まりの小港がある。これも珍しい。
川沿いに遡って、再びときわ大橋時計台の横にある中瀬邸に行く。ここは明治時代の商家で当時の様子が再現されている100円。足湯もあるらしい。なおこの近くには3時間まで無料(以後1時間わずか100円)の無料駐車場がある。
夏祭りで夜店の出る通りには、長沢青果もある。この通りは少し店舗が並んでいる。ここは大型店が松崎にこない中、昔ながらの買い物街のひとつということになるだろうか。
町中をつぶさに見たわけではないが、全体的な松崎の街の特徴は、昔の町の佇まいが残されていることかも知れない。
このように小売店、飲食店が残されている町が観光的に変貌する必要があるのか、それともこのままでいいのか考えた。
東伊豆稲取温泉のような、事務局長を招いての町興こしなどということが必要なのだろうか?
<pho1は依田邸、pho2は中瀬邸>

 |
|
| ■松崎町中心部 |
■ときわ大橋から、白井呉服店の横、土徳の十字路を右折して、観光協会、足湯、伊豆文邸と走って、国道136号線に出る。そして伊豆の長八美術館へ。 新しく鏝塚もできていた。 建物はユニーク。駐車場も広い。 国道136号を走って、あの東海バス松崎ターミナルへ。町の中心部らしく途中には銀行や郵便局がある。 バスターミナルのそばにも警察署やホテルも並ぶ。
<pho1は伊豆の長八美術館建物、pho2は美術館入口、pho3は東海バス松崎ターミナル>


 |
|
| ■帰一寺 |
■松崎の他のポイント、長八記念館のある浄感寺、神明水の湧く伊那下神社、名園のある浄泉寺、仏の小道、町民の森、伊豆松崎マリーナなどの他、岩科地区にある重文の学校、天然寺、なまこ壁の里などもあるのだろうが、1時間30分しかいないというのも妙。今度またという機会があるかどうか。
東海バス松崎ターミナルから県道15号線を走る。
|
|
| ■道の駅三聖苑 |
■帰一寺の少し先にある道の駅花の三聖苑に到着。
|
■梶寅旅館のこと |
 ある人気ブログの「映画つぐみについて語るスレ」で紹介されたのは、地元紙のつぎの記事。 ある人気ブログの「映画つぐみについて語るスレ」で紹介されたのは、地元紙のつぎの記事。
■「つぐみ」西伊豆松崎町-故郷の宿、今はひっそり 「廃業」の文字が、画面にあった。宿紹介のホームページを作った旅館組合に電話して、ちょっと驚いた。「ご主人がことし亡くなられたんですよ」 三島駅から西伊豆へ。電車と路線バスを乗り継いで二時間半。入り江の奥の、静かな船着場のそばに、宿はたっていた。特徴ある形の建物は、変わっていない。 「お風呂で倒れて。78歳でした。」松原しづ子さん(76)は、夫の他界後、一人で暮らしている。中伊豆の山あいから嫁いで54年になる。二人の娘も遠くへ嫁に行って年月がたち、家業を終える決心がついた。「なじみのお客さんも多かったですが。女手では骨の折れる仕事ですから」。 心残りはない、という穏やかな笑顔だった。 木造の建物は、昭和九年築。創業はそれより前の明治後期という。初代の寅吉さんが、船の「かじや」をやっていた。それで「梶虎」に。当時松崎は養蚕や木炭の産地として栄えた。港には多くの船が出入りし、旅館もにぎわった。 改築され、しゃれた外観になった梶虎は戦後、映画やCMのロケ地として注目される。何本の映画に登場したかは「数え切れない」(しづ子さん)。そのまま実名で宿が出てくるのは「つぐみ」が初めてだった。 物語は、旅館の娘つぐみ(牧瀬里穂)の幼なじみ、まりあ(中嶋朋子)の視点から描かれる。いったん故郷を離れたまりあは、松崎に帰ってきて”旅人”のような感覚になっている自分に気付く。一方、つぐみが恋人の恭一(真田広之)にもたれる防波堤のシーンがある。体が弱くて生まれ育った町を離れられないつらさをぶつけるつぐみに、恭一は「どこにでも行ければいい、というものではない」と諭す。 生まれ故郷で生きる人と、遠く離れた地から思う人。後者になって三十余年の記者は、古里の人々がうらやましく見える時がある。どっちが幸せなのか。映画を見ても答えが出なかったが、まりあが故郷に抱く「いとおしさ」は、痛いほど感じた。作品の公開時、梶虎には全国から若いファンたちが泊まりに詰めかけた。そんなロケの名所も、いまはひっそりたたずむ。まだ玄関先に出ている「つぐみの宿」の看板の前で、観光客が時折、写真を撮っていく。 「ここを借りたいという旅館業の方もいましたが。私は毎日、海を見るのがいい。窓から夕日がきれいで、前を船がゆっくり通って・・・。死ぬまでここに住みたいです」五十年を経て、松崎はしづ子さんの故郷になったのだろうか」(中日新聞2002年11月15日夕刊) これに対して、ある人のレスポンス。 「良い記事だ…。梶寅廃業の詳細知って納得しました。残された奥さんが高齢ではしょうがないですな。でも梶寅のあの建物だけでも残っているのがせめてもの救い。しかし何本ものロケに梶寅が使用されていたとは初耳。それにしても中日新聞のこの記事の記者さん、あんたココのスレの神だよ。もう「つぐみの部屋」に泊まれないのはなんとも惜しい……」 松原しづ子さんさんはそれから10年近くが経ち、86歳になっている。 地元の囲炉裏端さんの情報によれば「梶寅旅館の女将さんは存命だと思います。本当に何らかに利用されればとかねがね思っていました。しかし、風の噂では壊されるのではないかということです。見慣れた景色が消えることは残念なことです。この旅館には明治23年ごろ民俗学者の柳田国男が泊まったのです。個人資産ですのであまり口出しできないのです」とのことです。 取り壊しが本当であればとても残念。町の有形文化財として保存できないかとも思いますが。 しかし、ご存知の通り2000年の冬、梶寅旅館は解体されてしまったのはとても残念なこと。 |
■ |
 つぐみについて語る。
つぐみについて語る。
|
| ↑このページのトップへ | ||













